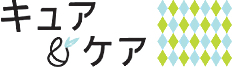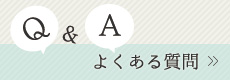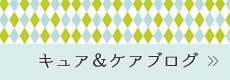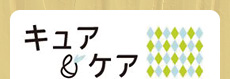HOME > キュア&ケアブログ > アーカイブ > 2015年4月
キュア&ケアブログ 2015年4月
いかり肩となで肩 解消ストレッチとこり防止エクササイズ
こんにちは、キュア&ケアの福田です。
今日は前回お話した、骨格の違いによる肩こりの症状の 解消ストレッチとその防止エクササイズ をご紹介いたします。
人は体を動かしていていると自然に力が入るものです。。
ストレッチをしている時は特に、力を抜かないときちんと伸ばしたい部位が伸びません。
抜いているつもりでも、意外に力は入っています。
ポジショニングがとれたら、一度呼吸とともに意識的に体の力を抜いてみてください。
これがポイントです!
いかり肩の方
1、ストレッチ
正面を向いたまま頭を横(例えば右)に倒します。
そこから目線を下に移すように頭を前側に倒していきます。床を見るような感じです。
反対側の肩(この場合左肩)が頭の動きにつられないように注意します。
肩にグッと力を入れる必要はありません。
その位置にキープしておくだけの最低限の力で、ほんのすこ~しだけ肩(左肩)を後ろに引きます。
肩から腕をダランとてを下げ、腕の重さを利用します。
2、ストレッチ
椅子に座り、両手で椅子の背をつかみます。
そのまま肩を下げ、体を前に倒していきます。
背中はなるべくまっすぐに保ち、腕に肩ががひっぱられていく感じです。
1、エクササイズ
両手を後ろに回し、腰(骨盤)の部分に手のひら(指が下に向くように)を当てます。
そのまま手を臀部のほうに下げるようにしながら背中に力をいれます。
10秒ほどキープしていったん力を抜く、を数回繰り返します。
僧帽筋下部線維に働きかけます。
なで肩の方
1、ストレッチ
いかり肩の ストレッチ 1 は共通です。上の説明を参考にしてください。
肩甲挙筋に働きかけます。
2、ストレッチ
椅子に深く座り背もたれに背中をつけます。
指を組んでその手を後頭部にあてます。
肘を軽く自然に閉じ、そのまま腕の重さを利用しながら頭を前に倒していきます。
頭を倒す角度や方向によって伸びる部分は変わりますが、まずは首筋を伸ばしてみましょう。
3、エクササイズ
両腕を軽く曲げ脇に添えます。
肩をすくめるように肩を持ち上げます。
この時、肩関節で肩を持ち上げるというよりは、首と肩の間の筋肉に力を入れ両肩を持ち上げます。
10秒ほどキープしていったん力を緩める、を数回繰り返します。
僧帽筋上部線維ひ働きかけます。
ふつう肩の方
上に挙げたストレッチを参考に自分に合った(気持ちいいと感じた)ものを試してみてください。
また、全体的にこわばりを感じると思うので、背中のストレッチも加えるとよいでしょう。
指を組んで手のひらを返し、その腕を正面に伸ばしながら背中は後ろに伸ばしていく。
腕と背中の伸ばしている角度を変えれば、いろいろな部位が伸びてきます。
今日は前回お話した、骨格の違いによる肩こりの症状の 解消ストレッチとその防止エクササイズ をご紹介いたします。
人は体を動かしていていると自然に力が入るものです。。
ストレッチをしている時は特に、力を抜かないときちんと伸ばしたい部位が伸びません。
抜いているつもりでも、意外に力は入っています。
ポジショニングがとれたら、一度呼吸とともに意識的に体の力を抜いてみてください。
これがポイントです!
いかり肩の方
1、ストレッチ
正面を向いたまま頭を横(例えば右)に倒します。
そこから目線を下に移すように頭を前側に倒していきます。床を見るような感じです。
反対側の肩(この場合左肩)が頭の動きにつられないように注意します。
肩にグッと力を入れる必要はありません。
その位置にキープしておくだけの最低限の力で、ほんのすこ~しだけ肩(左肩)を後ろに引きます。
肩から腕をダランとてを下げ、腕の重さを利用します。
2、ストレッチ
椅子に座り、両手で椅子の背をつかみます。
そのまま肩を下げ、体を前に倒していきます。
背中はなるべくまっすぐに保ち、腕に肩ががひっぱられていく感じです。
1、エクササイズ
両手を後ろに回し、腰(骨盤)の部分に手のひら(指が下に向くように)を当てます。
そのまま手を臀部のほうに下げるようにしながら背中に力をいれます。
10秒ほどキープしていったん力を抜く、を数回繰り返します。
僧帽筋下部線維に働きかけます。
なで肩の方
1、ストレッチ
いかり肩の ストレッチ 1 は共通です。上の説明を参考にしてください。
肩甲挙筋に働きかけます。
2、ストレッチ
椅子に深く座り背もたれに背中をつけます。
指を組んでその手を後頭部にあてます。
肘を軽く自然に閉じ、そのまま腕の重さを利用しながら頭を前に倒していきます。
頭を倒す角度や方向によって伸びる部分は変わりますが、まずは首筋を伸ばしてみましょう。
3、エクササイズ
両腕を軽く曲げ脇に添えます。
肩をすくめるように肩を持ち上げます。
この時、肩関節で肩を持ち上げるというよりは、首と肩の間の筋肉に力を入れ両肩を持ち上げます。
10秒ほどキープしていったん力を緩める、を数回繰り返します。
僧帽筋上部線維ひ働きかけます。
ふつう肩の方
上に挙げたストレッチを参考に自分に合った(気持ちいいと感じた)ものを試してみてください。
また、全体的にこわばりを感じると思うので、背中のストレッチも加えるとよいでしょう。
指を組んで手のひらを返し、その腕を正面に伸ばしながら背中は後ろに伸ばしていく。
腕と背中の伸ばしている角度を変えれば、いろいろな部位が伸びてきます。
(キュア&ケア)
2015年4月27日 09:30





いかり肩となで肩 コリの症状の違いと対策
こんにちは。キュア&ケアの福田です。
今日は、骨格の違いによるコリ のお話です。
皆さんは、ふつうの肩、いかり肩、なで肩、ご自分がいずれに当てはまるかご存知ですか?
まずは簡単にチェックしてみましょう。
鏡の前に立っていただいて、ご自分の鎖骨の位置を確認してください。
鎖骨のライン、首に近いほうと、肩に近いほうの位置はどうなっていますか?
比較的まっすぐなら ふつうの肩 です。
首に近いほうが低く、時計の針でいうなら 10時10分以上 ならば いかり肩 です。
首に近いほうが高くはの字 時計の針でいうなら 9時15分以下 ならば なで肩 です。
肩の形状に違いがあるということは、それぞれに筋肉のコリを感じる部分も違いますし、その対処法も異なってきます。
筋肉が収縮してコリを感じる部分は血行を促す必要があり、筋肉が引っ張られて伸びてしまっている部分は、エクササイズなどで筋肉の強化が必要になります。
•ふつうの肩
首、肩、背中と広い範囲でコリの症状を感じる
コリを感じる部分、首や背中など全体的に血行を促すと良い
•いかり肩
首と肩の上部にコリを感じやすい
いかり肩の人は肩甲挙筋(*1)と僧帽筋上部線維(*2)が収縮してこりを感じる
いわゆる肩が持ち上がっている状態なので、僧帽筋下部線維(*3)は引っ張られて伸びてしまい、筋力が低下して
いる
•なで肩
主に首にコリを感じる
なで肩の人は肩甲挙筋が凝っている
肩が下がり、僧帽筋上部線維が伸びている状態にあるため、重たい腕を肩甲挙筋が支えている
僧帽筋上部線維は筋力の低下がみられる
*1 肩甲挙筋: 頸椎と肩甲骨をつなぐ筋肉で、肩甲骨の上下運動にかかわる
*2 僧帽筋上部線維: 僧帽筋の上部に位置し、頸椎と肩甲骨をつなぐ。首をカバーし肩関節を持ち上げる動きに携わ
る
*3 僧帽筋下部線維: 僧帽筋の下部に位置し、胸椎下部と肩甲棘をつなぐ。肩甲骨を下に下げる動きに携わる
* 僧帽筋とは背中の表層にある三角形の大きな筋肉。重い頭の角度を保ち、上体を起こす働きがある
具体的なストレッチやエクササイズは次回にお伝えします。
今日は、骨格の違いによるコリ のお話です。
皆さんは、ふつうの肩、いかり肩、なで肩、ご自分がいずれに当てはまるかご存知ですか?
まずは簡単にチェックしてみましょう。
鏡の前に立っていただいて、ご自分の鎖骨の位置を確認してください。
鎖骨のライン、首に近いほうと、肩に近いほうの位置はどうなっていますか?
比較的まっすぐなら ふつうの肩 です。
首に近いほうが低く、時計の針でいうなら 10時10分以上 ならば いかり肩 です。
首に近いほうが高くはの字 時計の針でいうなら 9時15分以下 ならば なで肩 です。
肩の形状に違いがあるということは、それぞれに筋肉のコリを感じる部分も違いますし、その対処法も異なってきます。
筋肉が収縮してコリを感じる部分は血行を促す必要があり、筋肉が引っ張られて伸びてしまっている部分は、エクササイズなどで筋肉の強化が必要になります。
•ふつうの肩
首、肩、背中と広い範囲でコリの症状を感じる
コリを感じる部分、首や背中など全体的に血行を促すと良い
•いかり肩
首と肩の上部にコリを感じやすい
いかり肩の人は肩甲挙筋(*1)と僧帽筋上部線維(*2)が収縮してこりを感じる
いわゆる肩が持ち上がっている状態なので、僧帽筋下部線維(*3)は引っ張られて伸びてしまい、筋力が低下して
いる
•なで肩
主に首にコリを感じる
なで肩の人は肩甲挙筋が凝っている
肩が下がり、僧帽筋上部線維が伸びている状態にあるため、重たい腕を肩甲挙筋が支えている
僧帽筋上部線維は筋力の低下がみられる
*1 肩甲挙筋: 頸椎と肩甲骨をつなぐ筋肉で、肩甲骨の上下運動にかかわる
*2 僧帽筋上部線維: 僧帽筋の上部に位置し、頸椎と肩甲骨をつなぐ。首をカバーし肩関節を持ち上げる動きに携わ
る
*3 僧帽筋下部線維: 僧帽筋の下部に位置し、胸椎下部と肩甲棘をつなぐ。肩甲骨を下に下げる動きに携わる
* 僧帽筋とは背中の表層にある三角形の大きな筋肉。重い頭の角度を保ち、上体を起こす働きがある
具体的なストレッチやエクササイズは次回にお伝えします。
(キュア&ケア)
2015年4月19日 06:30





目の疲れが原因? 首や肩のコリ
こんにちは。キュア&ケアの福田です。
今日は、目の疲れからくる コリ のお話です。
毎日仕事でパソコンに向かい、プライベートではスマートフォンやゲームなどに没頭、ふっと気が付けば長時間集中して画面を見続けていたなんてこと結構ありますよね。
目がかすんだり、ショボショボしたり、目の奥が重く感じたり、そのうちに目を開けていること自体が辛く感じる人も多いのではないしょうか?
ただの目の疲れであれば、しっかり睡眠をとれば翌朝はスッキリと解消されているはずです。
しかし繰り返し、繰り返し、目を酷使することで疲れがたまり、睡眠や休息をとってもなかなかとれてこない。。
もしこのように慢性化している状態であれば 眼精疲労 へと進行しているのだと思います。
悪化すると頭痛や吐き気、耳鳴り、めまいなどの症状を訴える方もいます。
私たちがパソコンやスマートフォンを見るとき、目と画面との距離は近くなり、視点はあまり動かさないで一点(画面)に集中してしまいます。
この状態では、眼は常にピントを合わせるための筋肉(毛様体筋)を同じ状態でずっと使い続けていることになります。
画面を凝視すれば、まばたきする回数も自然に減り、目の乾燥(ドライアイ)を起こしやすいですし、目に入ってくる光も刺激となります。
様々な条件が眼の疲労を蓄積させていきます。
こうして目の疲労度が増してくると、筋肉や神経は過度の緊張によって収縮してしまい、やがて血行不良を起こしてしまいます。
血液の循環が悪くなっていると、疲労物質(乳酸)がうまく代謝されず滞り、その部分に新鮮な酸素と栄養が十分に供給できなくなってしまいます。
次第に目から頭全体へと影響がひろがり、頭皮もガチガチ、首から肩にかけてバリバリ、になってしまうのです。
目の疲れを解消するには、目を時々休ませたり、血行をよくするようなマッサージやツボ押し、温冷湿布をするなどが効果的です。
とは言え、集中してしまうとなかなか小まめにケアをすることなんて難しい、ですよね。。。
と言って何もしないと状況は変わらないので、何のかきっかけ、例えば咳を立つような時など、をケアするタイミングにして出来そうなことを習慣づけてみては如何でしょうか。
・目をギュ~ッと閉じたり開いたりする。
・目の周りの骨の上を指3本でゆっくり気持ちが良い程度の強さで押してツボ刺激をする。
・焦点が近くなっているので、少し遠くのものをしっかり5秒くらい見ては楽にする、を2~3度繰り返す。
・こめかみのあたりをツボ刺激する。
など、1つでも、2つでもちょっとした合間で簡単に出来そうなことをです。
しかしそれさえも忘れてしまったり、難しいと思われる方は、疲れを取るための 睡眠 を意識しましょう。
前述したように、眼精疲労は取れにくいものですが、寝ないと体を十分に回復させる出来ません。
人は寝ている間に、自然治癒力を言って、身体をもとの状態に戻そうという力を働かせるのです。
神経が緩まないので寝る直前までパソコンやスマートフォンを見ることは避けた法が無難です。
湯船につかり心身の緊張を緩めてみましょう。
ぐっすり安眠のための精油は、 ラベンダー、カモミールローマン、オレンジスィート、ベルガモット、 あたりがおススメです。
今日は、目の疲れからくる コリ のお話です。
毎日仕事でパソコンに向かい、プライベートではスマートフォンやゲームなどに没頭、ふっと気が付けば長時間集中して画面を見続けていたなんてこと結構ありますよね。

目がかすんだり、ショボショボしたり、目の奥が重く感じたり、そのうちに目を開けていること自体が辛く感じる人も多いのではないしょうか?
ただの目の疲れであれば、しっかり睡眠をとれば翌朝はスッキリと解消されているはずです。
しかし繰り返し、繰り返し、目を酷使することで疲れがたまり、睡眠や休息をとってもなかなかとれてこない。。
もしこのように慢性化している状態であれば 眼精疲労 へと進行しているのだと思います。
悪化すると頭痛や吐き気、耳鳴り、めまいなどの症状を訴える方もいます。
私たちがパソコンやスマートフォンを見るとき、目と画面との距離は近くなり、視点はあまり動かさないで一点(画面)に集中してしまいます。
この状態では、眼は常にピントを合わせるための筋肉(毛様体筋)を同じ状態でずっと使い続けていることになります。
画面を凝視すれば、まばたきする回数も自然に減り、目の乾燥(ドライアイ)を起こしやすいですし、目に入ってくる光も刺激となります。
様々な条件が眼の疲労を蓄積させていきます。
こうして目の疲労度が増してくると、筋肉や神経は過度の緊張によって収縮してしまい、やがて血行不良を起こしてしまいます。
血液の循環が悪くなっていると、疲労物質(乳酸)がうまく代謝されず滞り、その部分に新鮮な酸素と栄養が十分に供給できなくなってしまいます。
次第に目から頭全体へと影響がひろがり、頭皮もガチガチ、首から肩にかけてバリバリ、になってしまうのです。
目の疲れを解消するには、目を時々休ませたり、血行をよくするようなマッサージやツボ押し、温冷湿布をするなどが効果的です。
とは言え、集中してしまうとなかなか小まめにケアをすることなんて難しい、ですよね。。。
と言って何もしないと状況は変わらないので、何のかきっかけ、例えば咳を立つような時など、をケアするタイミングにして出来そうなことを習慣づけてみては如何でしょうか。
・目をギュ~ッと閉じたり開いたりする。
・目の周りの骨の上を指3本でゆっくり気持ちが良い程度の強さで押してツボ刺激をする。
・焦点が近くなっているので、少し遠くのものをしっかり5秒くらい見ては楽にする、を2~3度繰り返す。
・こめかみのあたりをツボ刺激する。
など、1つでも、2つでもちょっとした合間で簡単に出来そうなことをです。
しかしそれさえも忘れてしまったり、難しいと思われる方は、疲れを取るための 睡眠 を意識しましょう。
前述したように、眼精疲労は取れにくいものですが、寝ないと体を十分に回復させる出来ません。
人は寝ている間に、自然治癒力を言って、身体をもとの状態に戻そうという力を働かせるのです。
神経が緩まないので寝る直前までパソコンやスマートフォンを見ることは避けた法が無難です。
湯船につかり心身の緊張を緩めてみましょう。
ぐっすり安眠のための精油は、 ラベンダー、カモミールローマン、オレンジスィート、ベルガモット、 あたりがおススメです。
(キュア&ケア)
2015年4月11日 09:50





1
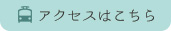
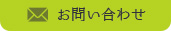
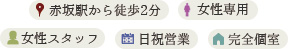
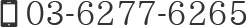 東京都港区赤坂6-4-18 プリンストン赤坂202
東京都港区赤坂6-4-18 プリンストン赤坂202